

ヨロン島で自給自足が出来る生活を目指す
アースカラーの緑が似合う松井鮎子さんは、ヨロン出身、4人姉妹の末っ子。学校から帰ったらサトウキビや牛の世話を進んでやる幼少期を過ごされました。
「女4姉妹だったから跡継ぎがいないじゃないですか。周りの人たちに、鮎子は畑が好きだから”うやむちぐゎー”(家を継ぐこと)せいってよく言われてたんですよ」
高校生の時は動物好きなことから獣医さんになりたかった鮎子さん。ある時、気候変動が原因で北極の氷が溶け、シロクマが危機的な状況をテレビで見て大きなショックを受けます。この時から、環境保全をして生き物を助けたいと思うように。
「最初は専門学校に通っていたけど、卒業後に東京環境工科専門学校という自然環境保全を学べる学校に進みました。その時の先生が、”地球規模で考えるんだけど足元から活動していけばいい”ってことを教えてくれて、自分の周りの自然を守ることをがんばろうと思えるようになりました」
 ▲NPO法人時代のイベント集合写真
▲NPO法人時代のイベント集合写真
卒業後はNPO法人鶴見川流域ネットワークに勤め、ビジターセンターの運営や子供たちと一緒に生き物を楽しむお仕事に従事。しばらくは東京で働いていた鮎子さんですが、専門学校時代に出会った旦那さまとの間にお子さんが生まれてから転機が訪れます。
「子どもが酷いアトピーで、なんでこんなことになるんだろうって調べたり勉強したら、食べ物が大切だと気付いて。普段食べているものが自分の子供に悪影響があることにショックで、自分らが食べるものを選ぶのも大事だけど、特に給食で有機の食べ物を入れることが、子供も農家も地球にもいいことだと講演会に行ったときに知ったんです。そこで、自分の生きがいはこれだと思って、ヨロンに帰ることにしました」
 ▲ヨロン島の田んぼで子どもたちと田植え
▲ヨロン島の田んぼで子どもたちと田植え
安心安全なやり方で生き物を増やして、みんながハッピーになるようにしたいと、田んぼづくりをがんばっている鮎子さん。人が一番食べている主食で、作るのが簡単なのはお米と講演会で聞き、ヨロンでも田んぼが作られていたので出来ると思い、チャレンジを決意。2023年には、与論町役場が主催する人材育成事業イノべーんちゅに参加し、お米作りをスタートさせました。2024年には初めて、町内の小学校でお米を給食に出すことが出来たそう!
「大きいんですけど、ヨロンの自給率をあげたいって夢があります。小麦や大麦、水を張らないおかぼ米、大豆とか、誰でも楽に出来るやり方を試行錯誤、確立できないかなって。いろんな人がやりやすいやり方を模索していきたいと思ってます」
気候変動により天候が予測しにくくなっている今、自給自足のニーズは高まっています。鮎子さんの挑戦は、今日も続きます!

松井鮎子(まついあゆこ)
会えるかもスポット:田んぼ
-
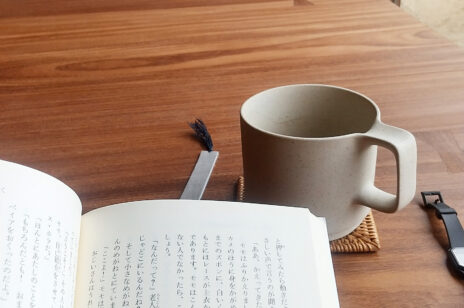
ヨロン島で本を片手にめぐる旅
『アイランド』に浸る1日プラン -

今こそ学び旅!
ヨロン島で大人の修学旅行2泊3日ツアー -

めがねのような旅がしたい
春のヨロン島2泊3日ツアー -

新年の始まりはヨロン島で!
南の島で年越しツアー -

インドア派でも楽しめる
ヨロン島一周サイクリングツアー -

まだ間に合う!
2023ヨロン夏旅★決定版★2泊3日ツアー -

カフェインは控えたいアナタに!
ヨロン島1日カフェインレスコーヒー旅 -

女子大生が行く、ヨロン島1日まるごと満喫旅
-

海を怖がる子どもでも、ヨロン島を満喫1日プラン
-

赤ちゃんと一緒にヨロン島を楽しむ2泊3日ツアー
-

ヨロンのオシャレカフェ満喫! 食い倒れ1日ツアー
-

誰とも喋らないで過ごしたい1泊2日ツアー
-

ヨロン島でプロポーズ大作戦 2泊3日ツアー
-

文化を感じる海沿いトレイル1日ツアー




