
ライターが見つけた旬の話題を独自取材しました。

海底湧水を学び、体感しよう
与論町大金久海岸にある渚の交番Ⅿuuruを拠点に子どもたちへ向けた学びの繋がりが広がっています。
2025年10月4日、「海の下のひみつの水、大発見! 海岸のわき水を探して、分析してみよう!」をテーマに海洋教育ワークショップが開催されました。これはNPO法人ヨロンSCが日本財団「海と人PROJECT」の助成をうけて、総合地球環境学研究所(地球研)との共催で行われました。ヨロンSCのスタッフである私も参加したその様子をレポートします!
当日は水環境問題を研究している琉球大学の安元純先生と、太古の気候変動を中心に研究している東北大学の浅海竜司先生の2名を講師に、参加したヨロン島の小学生及び保護者に向けて講話をいただいた後、海に行って海底湧水を実際に体感するという流れで行われました。
 ▲説明する琉球大学の安元先生(左から2番目)
▲説明する琉球大学の安元先生(左から2番目)
Muuruの建物内で世界トップクラスの流速の海底湧水についての話など、小学生むけにイラストをおりまぜながら講話を受けました。海底湧水について理解をしたあとは外に出て、大金久海岸の遊歩道から海底湧水のある場所まで歩いていきます。
前日に講師の先生たちと私たちスタッフで探し当てていた場所に、事前に海底湧水を計測する機械を設置していました。機械のまわりでは足元にひんやりと湧いてくる水の冷たさが感じられます。足の裏や手の平で触って感触を確かめた子どもたちは、「冷たい!」と他の場所との温度差にびっくりした様子でした。
しばらく湧水を体感した後、実際に計測が始まります。海底に沈めた円形のケースの上に袋を設置し、そこに入ってくる水の量を測定していきます。測定できる場所の流速としてはこの場所は世界トップクラスなのだとか!
その後、集めた水の塩分濃度を調べます。海水との塩分濃度が違うことで湧水であることがわかります。
実際に目の前で先生方が計測して証明してくれる様子をみて、子どもだけでなく大人たちも一緒になって「すごい!」「へー!」と感動した面持ちです。

▲海に潜って調べる子どもたち
太古の気候変動などを研究されている浅海先生からのお話もとても興味深く、「サンゴを年輪のように調べていくことで、何億年も前の地球の海の潮の濃さや雨の降り方なども分かるんです」とのこと。
参加者は「住んでいるけど知らなかった。もっとたくさんの人に知ってほしい」との感想が聞かれました。サンゴの年輪から太古の地球の様子がわかるなんて、ロマンですよね。
当たり前にあるヨロン島のきれいな海はふしぎな地下水が作ってくれているのかもしれない。そんな不思議を体験したワークショップでした。この奇跡のような自然界のバランスをこれからも大切にしていきたいです。
※このプロジェクトに係る記事は、NPO法人ヨロンSC主催で「シチズンサイエンスの土壌を育むワークショップ(公益財団法人日本財団助成)」の一環として実施しました。
-
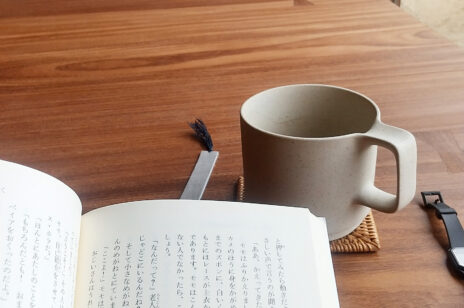
ヨロン島で本を片手にめぐる旅
『アイランド』に浸る1日プラン -

今こそ学び旅!
ヨロン島で大人の修学旅行2泊3日ツアー -

めがねのような旅がしたい
春のヨロン島2泊3日ツアー -

新年の始まりはヨロン島で!
南の島で年越しツアー -

インドア派でも楽しめる
ヨロン島一周サイクリングツアー -

まだ間に合う!
2023ヨロン夏旅★決定版★2泊3日ツアー -

カフェインは控えたいアナタに!
ヨロン島1日カフェインレスコーヒー旅 -

女子大生が行く、ヨロン島1日まるごと満喫旅
-

海を怖がる子どもでも、ヨロン島を満喫1日プラン
-

赤ちゃんと一緒にヨロン島を楽しむ2泊3日ツアー
-

ヨロンのオシャレカフェ満喫! 食い倒れ1日ツアー
-

誰とも喋らないで過ごしたい1泊2日ツアー
-

ヨロン島でプロポーズ大作戦 2泊3日ツアー
-

文化を感じる海沿いトレイル1日ツアー




